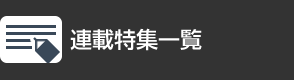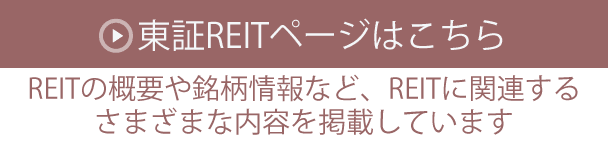■Event Report
【インフラファンド シンポジウム】
上場インフラファンド市場の現在
エネクス・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 山本隆行氏
カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 中村哲也氏
タカラアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 髙橋衛氏
アールジェイ・インベストメント株式会社 代表取締役社長 藤原勝氏
――インフラファンド市場に第1号案件が上場してから4年弱。これまでの歩みと手ごたえは。

タカラアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長 髙橋 衛氏
髙橋氏当法人は2016年6月、インフラファンドとして初めて東証に上場しました。インフラファンド市場がJ-REIT市場と別に創設された意義を考えてみると、大きく2点あると思います。ひとつは、当然のことながら投資ニーズの高まり。もうひとつは社会的な受け皿です。
2019年に閣議決定された第5次エネルギー基本計画のなかに「再生可能エネルギーの主力電力化をめざす」と掲げられています。安定した再生可能エネルギーを運用していくために、インフラファンド市場があると思っています。安定的に運用できる資産と能力をもつ我々を、再生可能エネルギーのプラットフォームとして活用するのもインフラファンド市場の役割ではないでしょうか。
2020年1月現在、上場6銘柄で保有資産1600億円強、時価総額900億円弱まで成長してきました。2月にはもう1銘柄が上場予定で、4月には「東証インフラファンド指数」も算出・公表されます。今後も上場銘柄みんなでまとまって市場拡大を進めていきたいですね。税制改正や買取価格、太陽光パネル廃棄など、インフラファンドだけでなく再生可能エネルギー業界全体で取り組むべき課題がまだまだ残されていますから。
藤原氏当市場開設以降、資産の積み上げ方針は各法人で違ってきているようです。たとえば、発電施設の設置場所が集中していたり分散していたり。もしくは、大型化して維持管理の効率化を図っている法人もあります。また、賃料設定も違ってきています。これは良し悪しではありません。投資家の皆さまの投資スタンスが違ってきているので、そのニーズに合った商品がそろってきているということです。
山本氏当法人は約1年前に上場した最も新しい法人です。先陣5法人が道を切り開いてきたわけで、上場当時もいまも、以前より投資家の皆さまの理解が深まってきている実感があります。
――2012年から、国が定める再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)が始まりましたが、足元では制度のあり方について当局で議論がされている状況です。FIT制度についての考えは。

アールジェイ・インベストメント株式会社
代表取締役社長 藤原勝氏
藤原氏「太陽光発電は終わった」かのような論調の新聞記事がありましたが、それはミスリードです。ただし、固定買取価格の決定プロセスがわかりづらいのは確かでしょう。この価格は国が勝手に決めるのではなく中立的な第三者委員会で決まり、太陽光発電施設の部材仕入れ価格や建設単価、事業者の利潤も考慮されています。したがって、その買取価格に対応する企業努力をすれば、今後も太陽光発電施設をつくって運営することができます。
買取価格の単価ばかりが注目されがちですが、より重要なのは20年間買い取ってもらえるという約束がされること。インフラファンドの運用においては、この安定したキャッシュフローは非常に大きな意味をもちます。実際に太陽光パネルの価格は数年前と比べると3~5割くらい下がっているなど、太陽光発電の開発はまだまだ十分な成長余地があります。
――電力の需給バランスを保つために電力会社がエネルギーの買い取りを一時的に停止できる「出力抑制(制御)」という制度があります。これについてはどうでしょうか。
中村氏実際のところ、当社の施設がある九州電力管内では2018年から日々の需給の関係で不規則的に行われています。再生可能エネルギーが主力電源化していくなかで、出力制限があるのは納得できない部分があります。
出力制限があったとしても、賃料収入がまったくなくなるわけではありません。当法人の場合、第三者による発電量予想の70%を賃料保証のような形で固定賃料にしているからです。ここで大事なことは発電施設の数を増やして分散させていくことでしょう。同一電力会社管内の太陽光発電施設がすべて一斉に制限されることはありませんから。
――2019年は天候不順の年でした。その対応はいかがでしたか。

エネクス・アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長 山本隆行氏
山本氏2019年は9月と10月に、関東中心に大きな台風被害がありました。当法人は茨城県に2つ発電施設をもっており、その1つで被害がありました。しかし、全パネル81000枚のうち、破損したのは0.1%にあたる100枚弱のみです。収益にそう大きな影響はありませんでした。破損原因を調べると、強風ではなく施設近くの倒木によるものが多かったようです。
復旧には数百万円単位の費用がかかりましたが、全額保険で対応しています。当法人は施設が全損しても対応できる保険、具体的には1年分の売電収入に耐え得る保険に入っています。被害復旧や逸失利益については保険で担保されているのでご安心いただきたいですね。また、天候被害や日射不足などへは、年間予想売電収入の10%をリザーブしているなど、安定した賃料スキームを構築してリスクに対応しています。
――ESG投資がグローバルの大きな流れになりつつありますが、インフラファンドとしての取り組みは。

カナディアン・ソーラー・
アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長 中村哲也氏
髙橋氏インフラファンドそのものがESGだといって過言ではありません。当法人は2019年、ESGの世界的なベンチマークである「GRESBインフラストラクチャー」に参加しました。獲得したレーティングは星4つ。GRESBインフラストラクチャーには世界で20のインフラファンドが参加していますが、そのなかで2位、アジアでは1位の評価です。
2019年に海外オファリングで増資した際に、海外の投資家を巡るロードショーを行いました。欧州の投資家はとくに、ESGへ高い興味を示しますね。その意味で、当法人のGRESBインフラストラクチャー評価取得は効果があったと思います。
中村氏再生可能エネルギーそのものがESGであるのは間違いありませんが、それだけでは十分でないというのが当法人の認識です。識者などの意見をお聞きすると、まずは国連の責任投資原則(PRI)に参加して、運用における物件の取得方針などの規約をよりESGに寄ったものにしてホームページなどで開示するのがよいと思います。インフラファンドは、投資口と銀行借り入れで資金調達していますが、今後はグリーンボンド(環境債)などもより大事になっていくでしょう。
――各法人の今後の展望は。
山本氏現在は上場から1年で資産規模180億円。今後5~6年でこれを1000億円にするのが当面の目標です。現在は太陽光発電がメインですが、当法人のパイプライン(取得機会が優先的に与えられる発電施設)には風力や水力もあります。電源のポートフォリオの拡大を進めていきたいですね。
中村氏当法人グループはもともと太陽光パネルメーカーですが、現在は川下部門の開発も世界中でおこなっています。日本でのパイプラインも三百数十メガワット相当あります。資産規模2000億円をめざして、この取得を進めていく計画です。
髙橋氏資産規模の拡大は計画的に進めていく一方で、インフラファンド市場全体の拡大を考えたいですね。J-REITと比べると、現状はまだまだ小さいです。市場全体の資産規模を拡大して流動性を高めることが重要でしょう。
藤原氏上場法人それぞれで“持ち味”が違ってきているなか、投資家の皆さまの観点も変わってきています。ファンドの成長はもちろん大事ですが、運用方針や仕組みをきちんと説明したうえで、投資家の皆さまのニーズにどのように応えていくのか。説明責任をこれまで以上に果たしていきたいと考えています。
※本記事は登壇者の発言を記者が独自に取り纏めたものであり、登壇者の発言内容を正確かつ網羅的に記したものではありません。
(次ページ) 【特別講演】J-REIT投資のポイントと2020年のマーケット展望① >>>
取材・執筆:K-ZONE (掲載日:2020年3月9日)