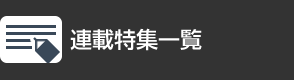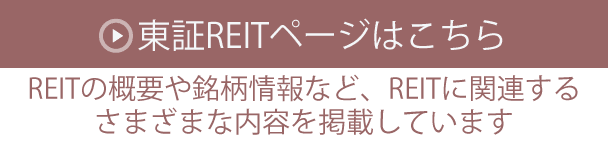■Event Report
【特別講演】
J-REIT投資のポイントと2020年のマーケット展望②
物件取得による増配に期待
SMBC日興証券 株式調査部シニアアナリスト 鳥井裕史氏
5年連続で5%増配中のJ-REIT

SMBC日興証券
株式調査部シニアアナリスト
鳥井裕史氏
J-REITは安定的なインカムゲインが期待できる商品というイメージですが、最近は1口当たり分配金がしっかり増えているという事実があります。2019年はJ-REIT全体で5%増配で過去5年間でも28%増、5年続けて5%増配しています。安定したインカムゲインに加えて、増配も期待できる商品であるということです。
2019年末の東証REIT指数は2145ポイントでした。私は2020年も5%増配を続けると思っています。賃料増加が非常にしっかりしており、物件取得での増配も期待できるからです。1口当たり分配金が5%増加すると、東証REIT指数の約100ポイントに相当します。つまり、2019年末の2145プラス100で2250ポイント、ここは底堅いのではないでしょうか。
今後の東証REIT指数は、長期金利の前提レベルとJ-REITに対してどの程度の増配を期待しているか、この2つが非常に重要です。私は2250ポイントをメインシナリオにしつつ、あわよくば2600ポイントを見に行く状況と考えています。その根拠を解説します。
増配維持しつつ長期金利+0.2%なら2400ポイントか
メインシナリオの2250ポイント達成のためには、5%増配をきちんとつくっていくこと。また、増配を期待し続けるのであれば、ある程度の金利上昇を織り込む必要があります。たとえば、5%増配で長期金利0.5%を前提にすれば、フェアバリューとして指数2250ポイントがはじき出されます。
国内外の機関投資家と話してみると、とくに地域金融機関は「増配を期待するというよりは、ゼロ金利が続くなかのインカムゲインはとても貴重」という意見が多く、J-REITに対して相当積極的です。そうなると、増配ゼロの純粋なインカムゲイン商品としてJ-REITを見た場合、長期金利0%ならこれもフェアバリューで2250ポイントになる計算です。
どちらも2250ポイントということで、大げさな数字でないことがおわかりいただけると思います。さらに、現実として5%増配を続けており、かつ長期金利はゼロより上がっていない状況なので、2600ポイントまでは説明できる水準といえます。ただし、2600ポイントまでいくと過熱感を指摘されるようになるので、まずは2250ポイントを見つつ間を取って2400ポイントです。5%増配を期待しつつ日銀が長期金利を-0.2%から+0.2%でコントロールしているので、上限である0.2%を取ればフェアバリューは2400ポイントになります。
スプレッド3.5%で指数2250ポイント、3.0%なら2600ポイント
東証REIT指数の2250や2600ポイントが、J-REITの分配金利回りから見て適正なのかを考えてみます。2250ポイントはJ-REIT全体の分配金利回りなら約3.5%、2600ポイントまでいくと3.0%程度になる計算です。この利回り水準は過去実績から見てどうなのか。
2019年は同指数が21%上昇した影響で、直近のスプレッド(J-REITの分配金利回りと長期金利の差)は下がっています。20年近くJ-REIT市場を見てきた経験からいうと、2013年から2015年ごろが最も“心地よい”スプレッドでした。当時は東京のオフィス市場(賃料)が回復し始めていましたが、期待がそう大きかったわけではありませんでした。期待も不安もそう大きくなく(=心地よく)推移していたスプレッドが3.0~3.5%と。現在もこのレンジがひとつの目安になるでしょう。結果として、スプレッド3.5%であれば指数は2250ポイント、3.0%なら2600ポイントになります。このレンジであれば安心して投資できるかなと、私は考えます。
2020年も好調が予想されるオフィス市場
私は昨年の本イベントで「オフィスと住宅、物流施設がよい、ホテルは厳しそうだ」と話しましたが、この流れは少なくとも今年前半は同じだと思っています。
オフィス市場は非常に強い状況です。東京都心5区のオフィス空室率は2%を下回っており、東京のオフィス需要が非常に堅調です。オフィス需要は就業者数と1人当たりの使用面積で決まります。東京の就業者数は過去4年間、年率2%のペースで増えており、とくに女性・高齢者の伸びがしっかりしています。企業からの就業ニーズも強く、この傾向はしばらく続くでしょう。
J-REITや日本の不動産市場は東京が最も重要で、たとえばJ-REITが持っているオフィス物件の3/4は東京です。この需要が年2%ずつ伸びるのであれば、空室率は2%程度に留まるでしょう。多少需要が減っても空室率は3%程度。2020年は供給がやや多いので多少は空室率が上がることが考えられますが。来年以降はまた落ちつくはずです。
住宅と物流もしっかり、商業施設とホテルは弱い
次に住宅市場です。賃貸マンションの賃料は上がっています。その背景にあるのは、大企業による人材確保のための家賃補助拡充です。2年ほど前までは低リスクプレミアム、ディフェンシブセクターといわれていた住宅市場ですが、ここ2年は5~10%ほど賃料が上がっており、この傾向はしばらく続くでしょう。リスクとして見ておかなければならないのは、従来の「安定セクター」という特徴が変わっていること。ディフェンシブではなく、企業業績にかなり影響を受けると思われる市場になっています。方向性としては今後、オフィス市場と同じように動くのではないでしょうか。
ショッピングセンター(SC)などの商業施設市場は、そう大きく動くことはないでしょう。郊外のSCがよくないのは事実。何とか横ばい維持してくれれば、くらいのイメージです。
物流施設市場はしっかりしています。景気が良かろうが悪かろうがEコマースが拡大傾向であることに間違いありません。ネット通販は景気の影響を受けることはもうないでしょう。2018年時点では、2019年は供給過多なので厳しいという見方がありましたが、実際は予想以上の需要がありました。物流施設には明るい見通しをもっています。
ホテル市場は今年も厳しいでしょう。2019年も供給過多で厳しかったですが、2020年後半から供給が減る見通しです。ただし、投資して1年待てるのならいいですが正直そこまで急ぐ必要はないと思っています。
たとえば、2018年から2020年にかけての累積3年間で、ホテルのトータルストックは25~30%増えており、このストックはインバウンドが4000万人にならないと捌けないといわれています。韓国や中国からの観光客が大きく盛り返しつつ、供給が減るのを待つしかありません。宿泊料も大量供給の影響で伸び悩んでいる状況です。
2020年は増資→物件取得→分配金利回り向上へ
2020年のJ-REIT投資のテーマとしては「物件取得」を挙げることができます。2019年のJ-REITの物件取得額は1兆4500億円で前年を下回る水準でした。2020年は少なくとも1兆7000億から8000億円、場合によっては2兆円くらいになる見通しです。物件取得がいかに増配へ寄与していくか、これが重要になるわけです。そこで、「物件取得キャップレート」が今年のJ-REIT投資判断を考える最も重要な指標になります。
J-REITの物件取得時には、新たに取得する物件のキャップレートと、J-REITの現在のポートフォリオのインプライド・キャップレートの2つの指標を確認することが重要です。キャップレートは、分子に取得予定不動産の賃貸純利益、分母に取得価格で算出され、また、インプライド・キャップレートは、分子にポートフォリオ全体の賃貸純利益、分母にJ-REITのネット有利子負債+時価総額で算出されます。投資口価格が上昇して時価総額が増えればインプライド・キャップレートは下がる計算です。
もし、キャップレートとインプライド・キャップレートが同じような水準だとしたら、増資して物件を買っても資産規模が拡大するだけで、1口当たり分配金は何も変わりません。一方で、インプライド・キャップレートより高いキャップレートで物件を買えば、増資で増配となります。
2015年から16年は、増資したら増配となって投資口価格が上がりました。しかし2018年は、毎月分配投信からの資金流出で東証REIT指数が低迷していた時期で、インプライド・キャップレートが上昇しました。その一方で不動産価格自体は上がり続けていたので、実際に取得する物件のキャップレートは下落。したがって、キャップレートとインプライド・キャップレートに違いがほとんどなく、増資しても1口当たり分配金の水準は何も変わらない状況だったのです。したがって、オフィス賃料がしっかり上がっているなら増資しない方がましだろうと、2018年は増資が嫌われる傾向がありました。
しかし2019年後半以降、東証REIT指数が2000ポイントを超えて、キャップレートとインプライド・キャップレートの差が2015~16年当時の状況に似てきました。ここからJ-REITは増資したら分配金が上がる環境です。実際に今年1月の8銘柄の事例では、増資によって4~5%の増配となっており、なかには11%も分配金が上がった銘柄もあるほどです。
※本記事は登壇者の発言を記者が独自に取り纏めたものであり、登壇者の発言内容を正確かつ網羅的に記したものではありません。
<<< 「J-REITファン2020」 個人投資家で盛況に (TOPページ)
取材・執筆:K-ZONE (掲載日:2020年3月9日)