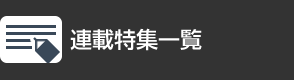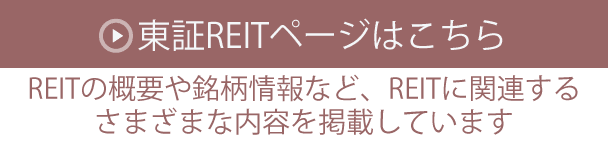■Event Report
【特別講演①】
不動産市況の現状と今後のJ-REIT市況の見通し
不動産エコノミスト
住宅・不動産総合研究所 理事長
吉崎 誠二氏
地方の地価上昇目立つ、マンション価格は天井か

不動産エコノミスト 住宅・不動産総合研究所 理事長
吉崎 誠二氏
9月19日に都道府県地価調査に基づく「基準地価」が発表されました。直近5年間における住宅地と商業地の地価を比べてみると、コロナ前より上がっています。住宅地の地価はおおむね、回復ではなく1つ先に行っているような状況。商業地は住宅地と違ってコロナ直前に上がっていたので、上昇率だけ見れば住宅地ほど戻っていません。しかし、2024年にかけて戻ってくるのではないかと見ています。
最近の傾向としては、3大都市圏の上昇率以上に地方の4大都市(札幌、仙台、福岡、広島)あたりの地価が伸びています。今後は、大規模な開発や工場の開設、イベントなどに影響を受けることは当然あるでしょう。詳しい説明は省きますが、地価はおおむね7年サイクルで動くという考え方を私は持っています。
マンション価格を見てみましょう。2013年ぐらいから現在まで、中古マンションは首都圏全体で、1.8~2倍くらいになっています。マンション在庫の売り出し価格と成約価格の差を取ると状況が見えてくるのですが、マンション価格はこの先、上昇トレンドが止まると思います。今年春先から「中古マンションはそろそろ天井感か」という話をしていました。ここに来て、言い切ってもいいぐらいの状況になってきました。
横ばい続くが変化の兆しが見えるJ-REIT市場
J-REITの最近の状況です。東証リート指数は1800ポイント台の半ば、1900ポイントにいかないあたりでしょうか。ここに来て若干、プロパティ(種類)ごとに差が出てきているようです。
オフィスは、在宅勤務から人が戻ってきているようで、東証REITオフィス指数もかなり戻ってきました。最近は横ばいという状況です。住宅は長期で見るとわかりやすいですが、比較的コロナの影響が少なく、東証REIT住宅指数も高い水準で安定感がある。物流は東証REIT商業・物流等指数を見ると苦戦していますね。一時期とても高かったので、現在は価格調整局面に入ってきているのかな、というところ。ホテルは戻ってきましたが、ここ1年だけ見るとほぼ横ばいです。
全体としては物流系が若干下げている以外は、ほぼ横ばいというのがここ最近の状況です。過去ほど大きな動きはないですが、今後は変わる気配が出てきていると思います。
東証REIT指数は不動産価格指数の動きに半年遅れ!?
東証REIT指数と国土交通省が発表している不動産価格指数を見ると、時期にズレがあります。先ほど、マンション価格が10年間で2倍ぐらいになった話をしましたが、東証REIT指数は2倍になっていません。特にここに来て乖離が生じています。
コロナ前によく言われていたのは、不動産価格指数の半年後ぐらいに東証REIT指数がその兆候を表してくるということ。金融緩和政策が意外と長く続いたことやコロナ禍、ライフスタイルの変化などで、現在はそう言い切れなくなっていますが、この半年のズレを信じて投資している方がいるのも事実。機関投資家の方のなかにも、妥当性があるという人がいらっしゃいます。
皆さんの判断にお任せしますが、東証REIT指数と不動産価格指数の「半年のズレ」は覚えていてもいいかもしれません。
利回りとNAV倍率を整理しておきます。昨日(9月29日)の終値で平均分配金利回りは4.16%。21年最終日が3.52%だったので、平均分配金利回りは約2割上がっています。1番低い銘柄が2.6%、1番高い銘柄は5.4%。ざっと平均して4%前後を維持しているのが、コロナ以降の傾向ということになります。
NAV倍率は株式投資におけるPBR(株価純資産倍率)と同じと考えていいと思います。直近で1番低い銘柄が0.6倍、高いのが1.19倍。60銘柄中、1倍超えが17銘柄しかないということで、この指標を参考に投資する方にとっては好材料と言えるでしょう。
物価上昇と賃料の関係は開示資料で確認を

今は物価上昇が続いています。金利も上がっています。金利上昇は借入利息が上がるので、少なくともLTV(総資産有利子負債比率)が低い銘柄がある程度、有利になります。借入金が固定金利か変動金利か、いずれをメインにしているかによって変わってきますが。
基本的に賃料は物価上昇値まで上がります。上がるのですが、賃料は「遅効性」「粘着性」という性質があり、新規賃料と継続賃料で違いが出てきます。新規賃料の上がり加減は、比較的ダイレクトに出やすいですが、継続賃料はそうでもありません。そのあたりを開示しているREITがあるのでチェックしてみるといいでしょう。
プロパティごとの見通しです。まずはオフィス系REIT。時価が大きい銘柄が多く、指数全体の動きに影響を与えやすいタイプです。大型オフィスビルは大手企業がテナントとして入っていることが多いので、安定性と収益性の高さがある一方、退去した際に埋める手間がかかります。NAV倍率は現在、0.76倍から1.1倍なので、やや弱含みというような状況です。
オフィスの供給量が多く今後が心配という声も聞こえます。オフィスの空室率が今は2割を超えていますが、東京都区部では、6%前後に留まっています。この先の供給量は減ることがわかっているので、需給バランスの心配はないかと思います。
住宅は地域分散、商業はEコマース、ホテルは中国動向に注目
住宅系REITの特徴は、不況期に強く安定性が高いこと。NAV倍率も0.92倍から1.07倍ぐらいで、1倍程度に収まっています。
住宅系のうち大型の特化型REITは3銘柄あります。東京都区部特化型なので、安定性は高いですが、首都直下型地震が発生した時の影響は考えておく必要があります。その意味では、物件地域が分散されている銘柄を考えてもいいでしょう。
商業系REITは、都市型と郊外型の2パターンあります。コロナショックの影響の大きさはさまざまありました。だいぶ回復基調にありますが、今後のEコマースの進展をどう見るかがポイント。日本人は結構、お出かけしたり買い物が好きですから。
ホテル系REITは、景気変動による影響が大きい。コロナの時もそうでした。天候や災害などにもかなり影響を受けます。イベントがあれば、大きく跳ねることもあります。この後、インバウンド需要がどこまで伸びるかで、大体見えてくるでしょう。訪日観光客全体の3割ぐらい占めていた中国からの訪日客が、まだ戻ってきていません。中国経済の動向が気になります。
株価下落傾向の物流はここから戻る可能性も
物流系REITは、ここ5年ぐらいで銘柄が増えました。現在は総合型と複合型を除けば、オフィスREITに次ぐ銘柄数になっています。オペレーショナルアセットの色合いが濃いのが特徴で、運営にはテクニカルな部分が必要です。ここ最近の株価下落要因の1つは、そもそも割高感があったこと、もう1つは物流施設の供給数が増えて、空室率が伸びていることが考えられます。
実際に物流施設は供給過多なのか、不足しているのか。いろいろな専門家と話をしてみると、まだ足りていないと見る方のほうが多いようです。今の株価は厳しい状況ですが、個人的にはここから戻り始めてくるのではと見ています。
総合型と複合型。今では全銘柄の半分ぐらいが総合型・複合型と呼ばれるREITです。複合型は住居とオフィスなど2つの種類を持つREIT。1銘柄でプロパティ別の分散が効くため、安定感があると言えるのかもしれません。オフィスと商業施設、住宅などのポートフォリオバランスに注意したいところです。
REIT投資は、REITの特性を理解して資産ポートフォリオを組んでいきたいですね。安定的なインカムゲインが期待できるので、長期保有の前提がいいでしょう。現物の不動産投資が好きな方も、まとまった資金が必要など積極的に行うことには限界があります。そこで、少額から投資可能で透明性の高いREITを資産に組み込んでいくのは合理的だと思います。
※本記事は登壇者の発言を記者が独自に取り纏めたものであり、登壇者の発言内容を正確かつ網羅的に記したものではありません。